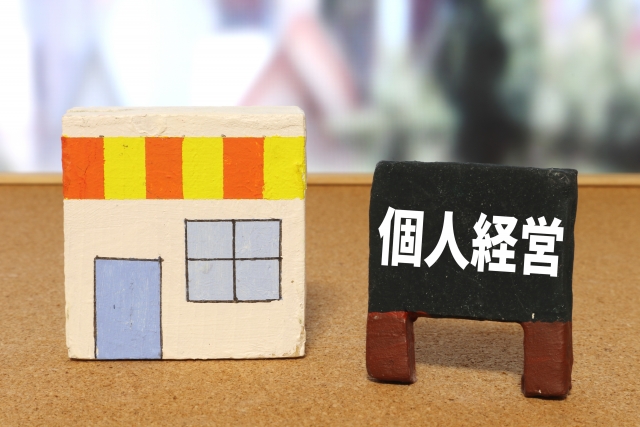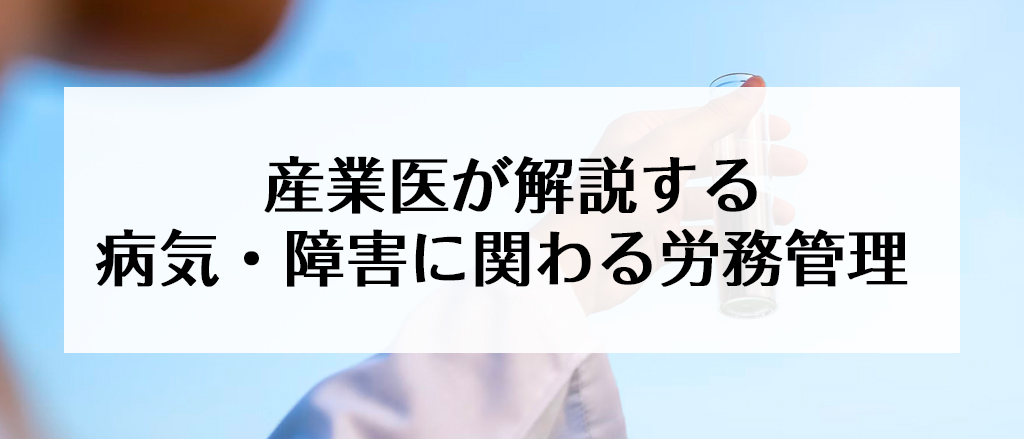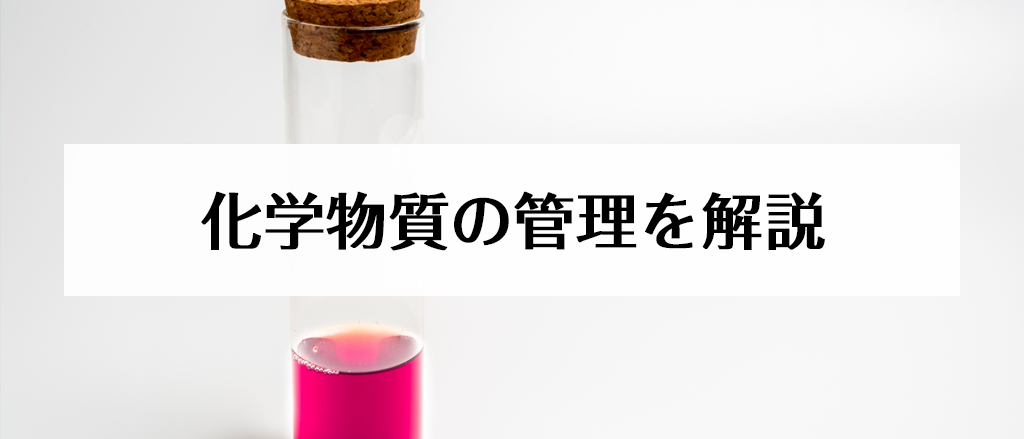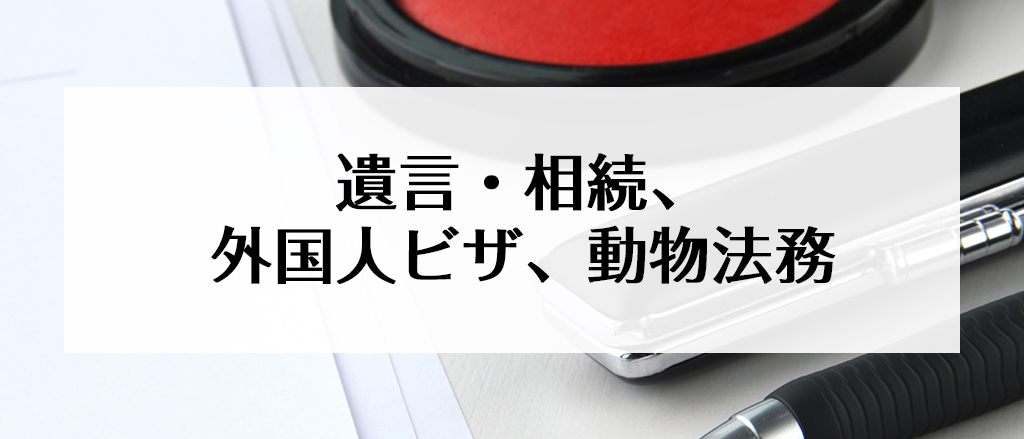2025/04/05 2023/04/20
【資格・産業医向け】労働衛生コンサルタントは開業を前提とした資格であり、登録後の注意事項を説明

産業医としてのキャリアを考える中で、「将来的に開業も視野に入れている」という先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
開業形態としては株式会社などの法人を設立することが一般的ですが、この場合に労働衛生コンサルタント事務所として登録・活動する方法もあります。
今回は、産業医専門の開業を目指す先生方に向けて、労働衛生コンサルタントとはどのような資格か、士業としての側面や、産業医業務との関係性などについて、少しマニアックではありますが詳しく解説したいと思います。
将来の選択肢のひとつとして、参考になれば幸いです。
労働衛生コンサルタントについて
労働衛生コンサルタントは「士業」か?
2022年だったような・・・・厚生労働省のホームページに見慣れない文言を見つけました。
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働衛生のスペシャリストとして、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)です。
厚生労働大臣が指定したコンサルタント試験機関である(公財)安全衛生技術試験協会が実施する労働安全コンサルタント試験・労働衛生コンサルタント試験に合格し、厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会に登録することで、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントとして活動することができます。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_04164.html
厚生労働省の資料では、「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは・・・国家資格(士業)です」と明記されています。
そう、「士業」とハッキリ書かれているのです。
士業といえば、いわゆる「八士業(はちしぎょう)」が有名ですね。弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などが含まれ、それぞれが特定の法律に基づいて、独占業務を有する専門職です。これらの士業は、無資格者が業務を行うと法的な罰則が科される場合もあります。
労働衛生コンサルタントに関しても、
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則」という省令が存在しており、一定の制度設計がなされています。
しかし、私自身がこの点について、厚生労働省に確認したところ、
「ここで言う「士業」とは、専門性を有する国家資格であるという意味合いで使用しており、他の士業のように独占業務や厳格な事務所要件があるわけではない」とのことでした。
つまり、従来通り、労働安全・衛生コンサルタントについては柔軟な運用が可能で、他士業ほどの制限はないというのが現状のようです。
とはいえ、法令上においても、すでに労働衛生コンサルタントは「士業的」な位置づけに近い規定が存在しています。
もし将来的に士業としての法的位置づけが強化されることになれば、事務所要件や連携体制、名称使用の制限など、今後の活動に影響が出てくる可能性も否定はできません。
労働衛生コンサルタントは「開業が前提」の国家資格です
労働衛生コンサルタントの業務に関する条文
実は、労働衛生コンサルタントという資格は、他の士業と同様に開業が基本形となっている国家資格です。
開業してはじめて、法的に労働安全衛生コンサルタントとして活動できることになっており、逆に言えば、開業せずに在籍するだけでは正式なコンサルタントとは見なされません。
この点には明確な法的根拠があります。
労働安全衛生法
この、「他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため・・・・・・を行なうことを業とする」者が労働衛生コンサルタントです。
この「他人の求めに応じ報酬を得て」とはどのような意味を持つのでしょう。
実は、ここがポイントです。
社会保険労務士の規定にも見る「開業」の定義
労働衛生コンサルタントに関する法令(労働安全衛生法 第81条)では、
「他人の求めに応じ報酬を得て・・・診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする」という文言が使われています。
実は、この表現は他の士業の開業を定義する条文にも登場しています。代表的な例が、社会保険労務士法です。
労働衛生コンサルタントの「開業が前提」であるという点について、実は社会保険労務士(社労士)の制度と非常によく似た構造があります。
では、社労士の開業の法的根拠を見てみましょう。
それは、社会保険労務士法 第14条の2第 2項に記載されています。
ここでは、「報酬を得て業として行う=開業」であり、そのためには事務所を定めて登録することが法的に義務付けられていることが明記されています。
ここで出てくる「他人の求めに応じ報酬を得て」という表現は、労働衛生コンサルタントの規定(労働安全衛生法第81条)にもまったく同じ言い回しが使われています。
社会保険労務士法
(登録)
第十四条の二 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
そして、「社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 」とも記載されています。
社会保険労務士は登録が必要なのです。
また、社会保険労務士法第18条には、開業社会保険労務士について、以下のように明確に記載されています。
(事務所)
第十八条 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
ここでのキーワードは、やはり「他人の求めに応じ報酬を得て」という表現です。
これは、開業という概念を法的に定義する重要なフレーズとして位置づけられています。
実は、「他人の求めに応じ報酬を得て」という表現は、開業社会保険労務士の定義として用いられており、これが“開業”の意味を持つキーワードであると解釈されています。
このことから考えると、労働衛生コンサルタントに関する規定においても同様に用いられている「他人の求めに応じ報酬を得て」という文言は、開業を前提とした制度設計であることを示していると解釈することができます。

こは、労働安全・衛生コンサルタントの登録事項はどのような者でしょうか。
労働衛生コンサルタントの登録について
では、労働衛生コンサルタントの登録はどのように定められているのでしょうか。
社会保険労務士については、「社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 」と、社会保険労務士名簿への登録が必要でした。
労働安全・衛生コンサルタントの登録制度については、労働安全衛生法84条と、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(通称、コンサル則)16条に記載があります。
これらの条文により、労働衛生コンサルタントも、厚生労働大臣による登録を受けなければ業務を行うことはできないとされており、さらに、登録に際しては専用の事務所を定め、所在地や名称などの情報を届け出る必要がある点でも、社会保険労務士と非常に類似した構造を持っています。
労働安全衛生法
(登録)
第八十四条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
こちらは、コンサル則です。
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
(登録事項)
第十六条 法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称
二 生年月日
三 合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日
四 事務所の名称
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
これによると、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、コンサル則16条の事項を登録しなければならないということになっています。
ここで、事務所の名称等の登録が必要となりますが
例えば登録先が自分の勤務場所であれば
①病院の雇われ勤務医が職場の病院の所在地内に「〇〇労働衛生コンサルタント事務所」の看板を勝手に掲げる。
②株式会社の産業医が、自分の職場内に勝手に「〇〇労働衛生コンサルタント事務所」を開業している
③大学の教員が、自分所属する教室に「〇〇労働衛生コンサルタント事務所」を開業している
ということになり、問題になると思いませんか。
ちなみに、労働衛生コンサルタント登録申請書(様式第3号)には「事務所の名称及び所在地」を記載しなければなりません。
たとえば、労働衛生コンサルタントとして登録している場所以外の法人(例:株式会社など)のプロフィールに「労働衛生コンサルタント」と記載する場合、注意が必要です。
というのも、登録していない場所で労働衛生コンサルタント事務所を表示・活動してしまうと、形式上、「2か所目以上の事務所を開設している」と見なされる可能性があるからです。
労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣への登録制度の下で、事務所の所在地・名称を届け出たうえで活動することが義務付けられており、複数事務所の設置には制限があります。
ただし、ここでひとつ重要な、労働安全・衛生コンサルタントに適用される特例があります。
後述しますが、労働衛生コンサルタントは、他の一部士業と異なり、二か所以上の事務所を登録することが可能です。
これは、「従たる事務所」として正式に登録を行えばよく、主たる事務所と合わせて複数拠点での活動が認められている制度です。
したがって、たとえば別法人(例:株式会社)のプロフィールに「労働衛生コンサルタント」と記載したい場合でも、その場所を従たる事務所として正式に登録しておけば、法的には問題ありません。
逆に言えば、従たる事務所としての登録を行わずに活動や表示を行ってしまうと、登録外の事務所を開設していると見なされるリスクがあるということになります。
この点は、本来であれば士業としての自覚や、表示に対する責任、そして登録制度に対する正確な理解が求められる重要な部分です。
しかしながら、実際の現場ではあまり重要視されていないのが現状です。
そのため、登録していない法人のプロフィール等において、コンサルタント事務所であるかのような表示を行うことは、法的な観点から不適切とされるおそれがあります。
ちなみに、私は、他の会社で労働衛生コンサルタントの属性を記載するときは
「労働衛生コンサルタント事務所LAO 労働衛生コンサルタント 清水宏泰」
と記載します。事務所が別だときちんと明言しているわけです。
したがって、株式会社のプロフィール欄や、病院のスタッフ紹介、大学教員の経歴紹介などに「労働衛生コンサルタント」と記載することは、厳密には適切ではありません。なぜなら、それらの場所は正式に登録されたコンサルタント事務所ではない場合が多く、登録外の事務所で活動していると見なされる可能性があるからです。
ちなみに、社会保険労務士や行政書士といった他の士業では、株式会社の中で個人として開業することは制度上認められていません。
つまり、法人と士業を同時に並立させることには明確な制約があります。
一方で、たとえば個人開業医が自身の診療所で労働衛生コンサルタントを兼ねるという形であれば、その診療所を労働衛生コンサルタントの事務所として登録すれば制度上問題はなく、実質的な兼業が可能になります。
賃貸物件での事務所登録は賃貸借契約の制限がある場合があります。
また、自宅を労働衛生コンサルタントの事務所として登録する場合にも注意が必要です。
特に賃貸物件の場合、賃貸借契約において「事業用途での使用を禁止する」条項が含まれていることが多く、
そのようなケースでは、原則として事務所としての登録は認められない可能性が高いと考えられます。
したがって、自宅での登録を検討する場合には、契約内容を十分に確認し、事業利用が可能かどうかを事前に管理会社や貸主に確認することが不可欠です。
労働衛生コンサルタント事務所の複数登録について
前述のとおり、労働安全・衛生コンサルタント事務所は、複数の拠点を登録することが可能です。
実際に、登録申請時に使用する『コンサルタント登録申請書(様式第3号)』の備考欄にも、次のように明記されています。
「従たる事務所がある場合には、その名称及び所在地を併記すること」
さらに、私が登録窓口である安全衛生技術試験協会に確認したところでも、複数事務所の登録は可能であるとの回答を得ています。
これは、多くの他士業が原則として1か所しか事務所登録ができないという制度設計になっているのに対し、労働衛生コンサルタントは柔軟に複数拠点での業務展開が可能な点で、やや特異な制度です。
また、複数の事務所にかかる経費についても、事業所得としての処理が可能となる可能性があります。
この点については税務の専門的な判断が必要となるため、必ず税理士に相談するようにしましょう。
指定登録機関 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 殿
コンサルタント登録申請書(様式第3号)
備考
1 厚生労働大臣が登録事務を行う場合には厚生労働大臣に提出すること。この場合にあっては、手数料に相当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けること。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合には当該指定登録機関に提出すること。この場合にあっては、当該指定登録機関の登録事務規程に定めるところにより手数料を納付し、収入印紙は貼らないこと。
3 「氏名」の欄は、旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無を〇で囲むこと。併記を希望する場合には、併記を希望する氏名又は通称を記入すること。
4 ④欄は、従たる事務所がある場合には、その名称及び所在地を併記すること。
5 ⑥欄は、合格証の年月日を記入すること。
6 申請書には、合格証の写しを添付すること。
まとめ
(登録について)
労働衛生コンサルタントは労働衛生コンサルタント名簿に登録が必要であり、社会保険労務士は社会保険労務士名簿に登録が必要
(業として)
労働衛生コンサルタントは、「他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るための助言や指導を行うことを業とする」と定義されています。
一方、開業社労士は「他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の職務に規定された業務を行おうとする」専門家です。
「他人の求めに応じ報酬を得て」という点が開業の要点となります。労働衛生コンサルタントは、開業を前提とした資格であることを意味します。
(おまけ:労働衛生コンサルタント試験において)
労働衛生コンサルタントの試験では、「コンサルタントになったら、どのような活動をしたいですか」という質問が出題される可能性が高いです。
開業を前提とする場合、この質問に対する回答が重要になるでしょう。意外にもこの部分が試験のポイントであり、合否を分ける要素となるのでは?と私は考えています。
大学教員 〇〇 資格:労働衛生コンサルタント
となると、どこかの大学の中で労働衛生コンサルタント事務所を開いていることになってはおかしいですよね。
労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。