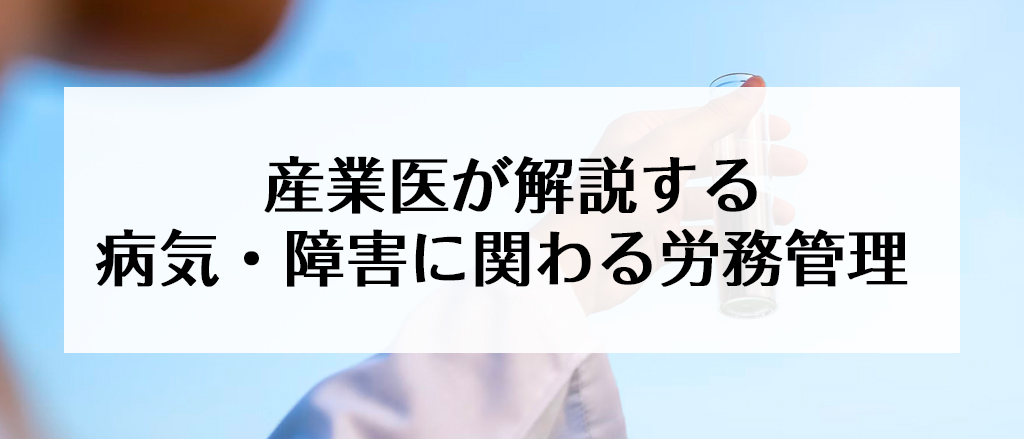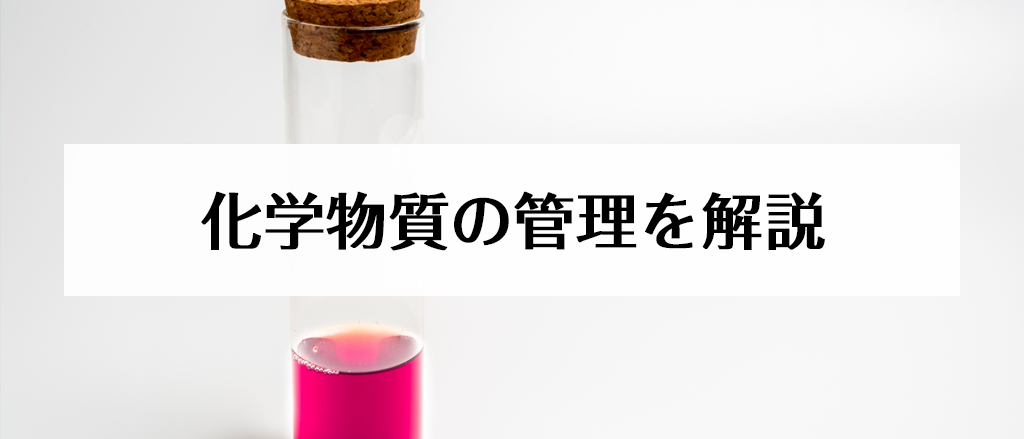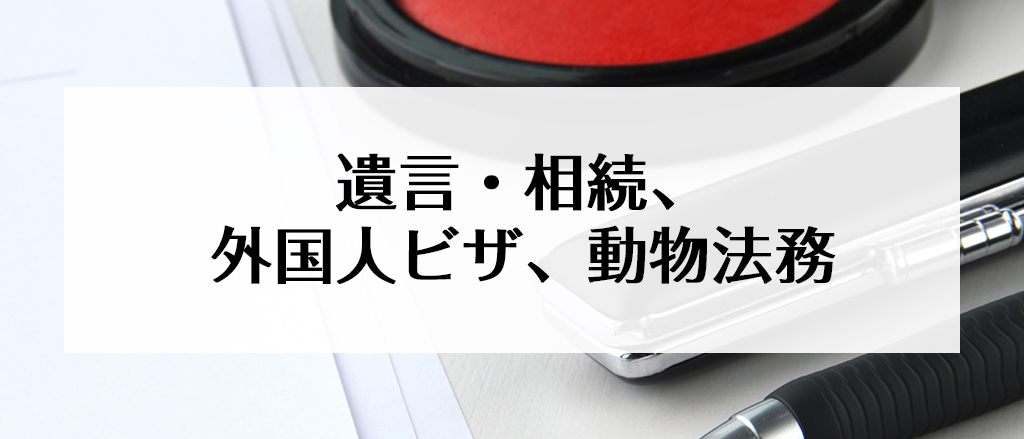2023/05/11 2023/05/11
【産業医・人事労務担当者向け】配置転換(配転)についての基礎知識と論点について
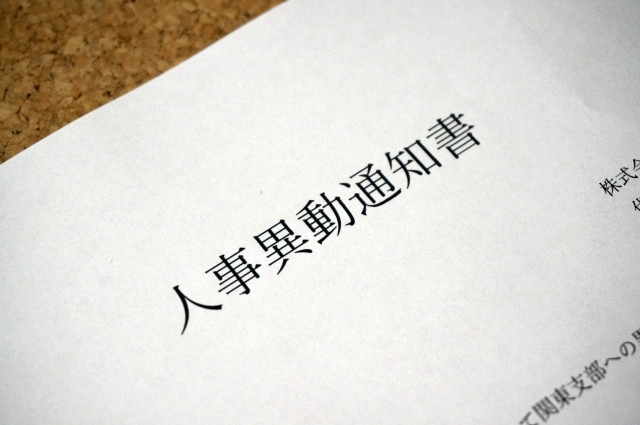
よく、産業医の講義等で産業医は配置転換の意見も述べましょうという話があります。
しかし、配置転換に関する論点については解説されないことが多いかと思います。
今回はそちらを解説したいと思います。
配置転換についての基礎知識と論点について
配置転換とは
まず、配置転換とは何でしょう。配置転換は、配転とも言われますが、配転の定義は以下になります。
配転とは、同一企業内での労働者の職種・職務内容または勤務場所の変更であって、相当の期間にわたって行われるもの
皆様、この定義は知っていましたでしょうか。
産業医の就業上の措置により、職務内容を今後変更するという場合には、配転に当たります。
配転を行う上で、働く人々が自分なりに職業生活を準備し、開始し、展開することを基礎づけるキャリア権という考え方も知っておきましょう。
そもそも、 使用者が配転命令を行使できるかどうかについて
まず、配転を使用者が労働者に命ずる権利を配転命令権といいますが、そもそも使用者に配転命令が可能かが問題となります。
配転命令権があるかどうかは、労働契約・就業規則等によります。
労働者が従事する業務の内容、終業の場所は、労働契約の基本的な内容であり、労働条件通知書にも記載が必要です。
この点、配転に関する取り決めがあれば、その取り決めが優先されます。
さらに、こちら労働契約と就業規則の効力については労働規約法7条にも記載があります。
但書きが重要で、労働条件に特約があれば、そちらが優先されます。
従事する場所につき特約があるかどうかのチェックも必要です。
労働契約法
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
e-Gov 労働契約法
まとめますと、そもそも、使用者が労働者に配転を命じるには、労働契約、労働協約、就業規則等によって配転命令権が根拠づけられている必要があります。
配転に関する権利濫用法理(東亜ペイント事件)
さて、配転に関して、使用者に配転命令権があることを前提として、配転命令の行使が適当であるかどうかの問題があります。
判例がありますのでご紹介しましょう。
東亜ペイント事件においては、配転に関する権利濫用法理が問題となっています。
権利濫用法理は、労働契約法3条5項に記載があります。
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
e-Gov 労働契約法
この判例の権利濫用となるポイントですが以下の東亜ペイント事件判例の黄色ハイライト部分になります。
東亜ペイント事件 (S61.07.14最二小判)
【事案の概要】
(1) 頻繁に転勤を伴うY社の営業担当者に新規大卒で採用され、約8年間、大阪近辺で勤務していたXが、神戸営業所から広島営業所への転勤の内示を家庭の事情を理由に拒否し、続いて名古屋営業所への転勤の内示にも応じなかったことから、Y社は就業規則所定の懲戒事由に該当するとしてXを懲戒解雇したところ、Xは転勤命令と懲戒解雇の無効を主張して提訴したもの。
(2) 最高裁は、転勤命令は権利の濫用であり、Y社が行った転勤命令と、それに従わなかったことによる懲戒解雇は無効であるとした大阪地裁・高裁の判決を破棄し、差し戻した。
【判示の骨子】
(1) 入社時に勤務地を限定する旨の合意もなく、労働協約と就業規則に転勤を命じることができる旨の定めがあり、転勤が実際に頻繁に行われていたという事情の下では、会社は、労働者の個別的な同意を得ることなくその勤務場所を決定できる。
(2) しかし、特に転居を伴う転勤は、労働者の生活に影響を与えることから無制約に命じることができるものではなく、これを濫用することは許されない。
(3) そして、転勤命令について、業務上の必要性がない場合、その必要性があっても他の不当な動機・目的をもってなされた場合、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等、特段の事情がない場合には、当該転勤命令は権利の濫用に当たらない。
(4) なお、業務上の必要性とは、その異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することなく、企業の合理的運営に寄与する点が認められる場合を含む。
(5) 本件転勤命令には業務上の必要性が優に存在し、Xに与える不利益も通常甘受すべき程度であり、権利を濫用したとはいえない。
以上より、以下の要件を満たす場合には、転勤命令が権利濫用となります。
(1)業務上の必要性がない場合
(2)必要性があっても
①他の不当な動機・目的をもってなされた場合
②労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
等、特段の事情がある場合
(1)または(2)の場合は権利濫用となりえます。
まとめます、使用者に配転命令権が認められる場合も、①配転命令に業務上の必要性が存しない場合、②配転命令が不当な動機・目的に基づく場合、③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼす場合には、配転命令は権利濫用として無効となります(労契法3条5項)。

産業医業務の実務について
以上より、産業医が勤務地を変更する必要のある配置転換の意見を述べる場合には、当該従業員の労働条件通知書・労働契約書を確認し、さらに、労働協約と、就業規則に転勤の定めがあるかという点もチェックすべきポイントになります。
産業医の仕事としては、この業務ができないという部分で意見を述べるだけです。
あくまで労働契約・労働条件の範囲内でどちらに配転させるかは事業者の裁量になります。
しかし、この事業者の裁量において権利濫用法理等が問題となりうることがあります。
できれば最初からトラブルを避けたいですよね。
これらを勘案・調整して、就業上の措置の意見を述べるとトラブルが少ないでしょう。
もし、配転できる業務が契約等にないけれど、どうしても配転せざるを得ないときは
もし、労働契約・就業規則等の範疇に、配転できそうな業務がない場合には、配転について会社と従業員で相談してもらいましょう。
ひょっとしたら、合意により、労働条件を変更できるかもしれません(労働契約法8条)。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
まとめ
産業医の意見としての就業上の措置については、実際の健診データーや主治医の診断書、診療情報提供依頼書に基づくことが殆どであり、就業上の措置自体が権利濫用にあたることはあまりないと思います。
そもそも、配転ができるかどうか、どのように行うのかの配転に関する取り決めがあるかどうかのチェックが重要になってくるでしょう。
また、あらかじめ配転できる範囲がわかっていれば、主治医に診療情報提供依頼書を発行する際の文言もかわってくるのではないでしょうか。
どうしても従前の労働条件にない業務・場所に配転を命じる場合には、合意で労働条件を変更することも考慮しましょう。
労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。