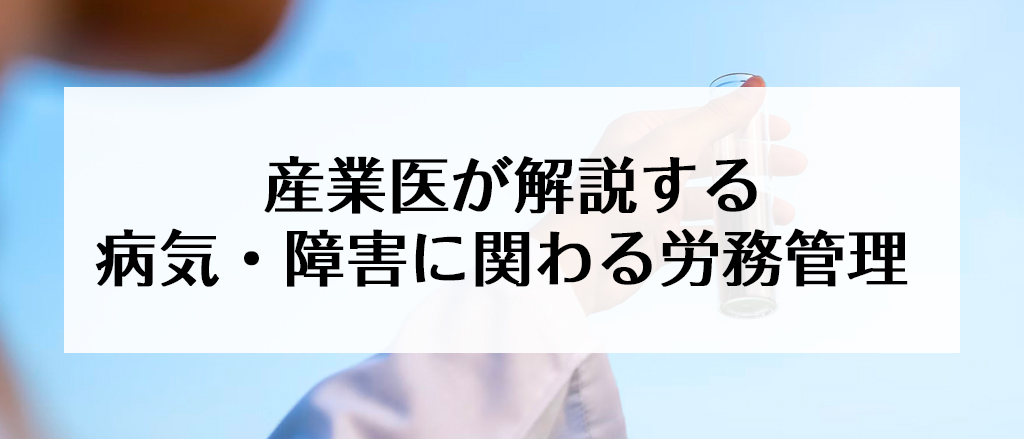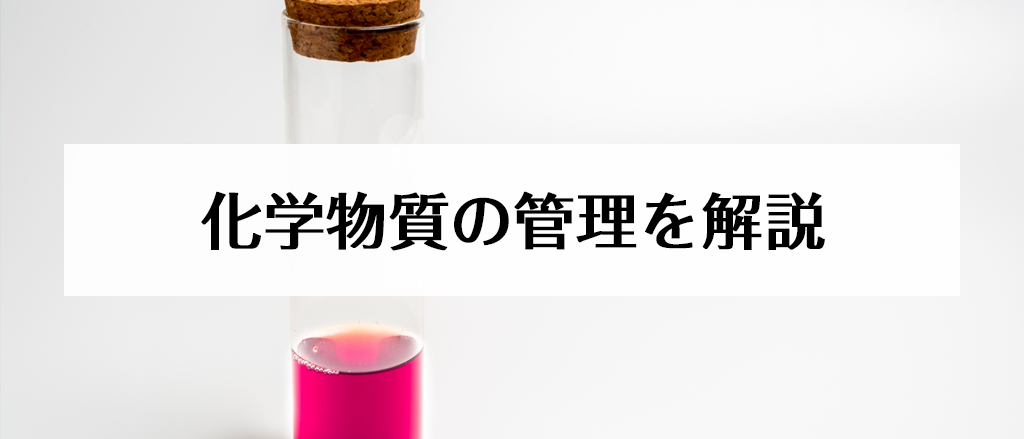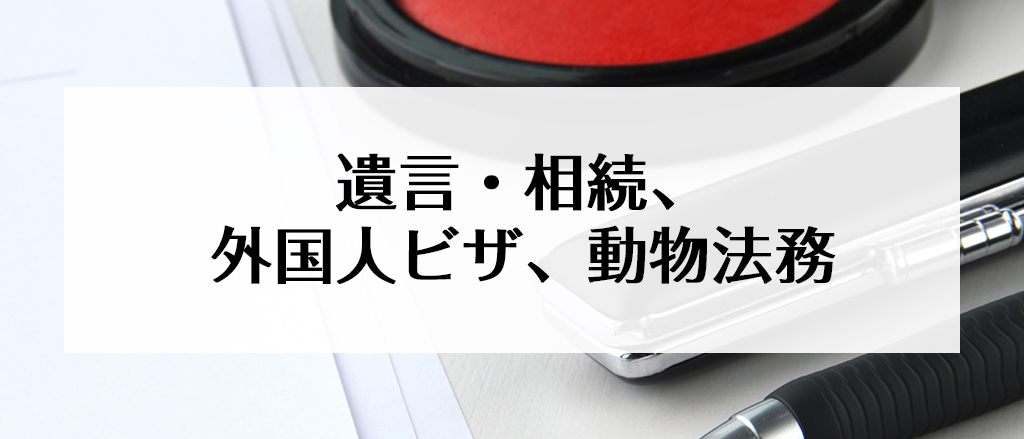2025/06/04 2023/04/13
【初心者・産業医向け】診療情報提供依頼書の主治医への送付と特定記録について
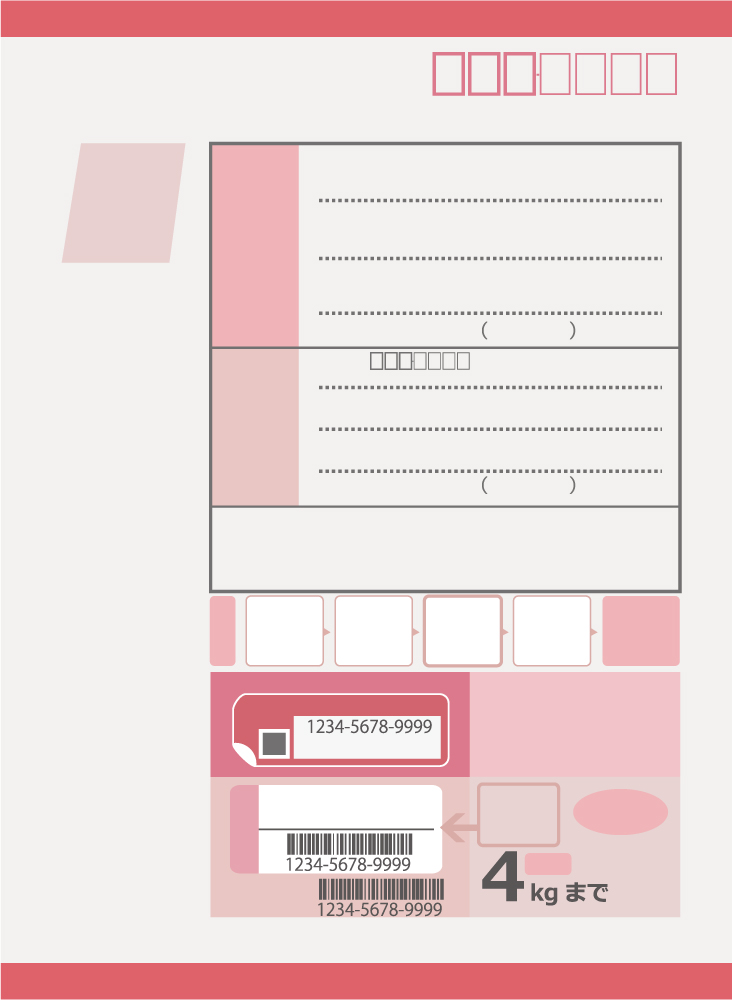
産業医と主治医の間では、通常、書面による情報交換が行われます。一般的には、受診者に産業医が作成した書面を主治医へ持参してもらう形多いかと思いますが、場合によっては、産業医から主治医へ直接書面を送付することもあります。
しかし、このような場合、書面が確実に主治医の元に届いたのか不安になることもあるのではないでしょうか。
今回は、そうした不安を解消するための具体的な方法についてご紹介いたします。
主治医への書面の送付
主治医へのお手紙送付の必要性
産業医が主治医と書面で情報をやり取りすることは、産業保健の実務において決して珍しいことではありません。私自身も、日常的に主治医との書面による連携を行っています。
しかしながら、実際には主治医との連携をあまり重視しない産業医も存在しています。とはいえ、今後の産業保健の現場においては、主治医との連携は「職場復帰支援」や「治療と仕事の両立支援」に不可欠な要素です。これからの時代、主治医への書面(診療情報提供依頼書)を適切に発行しない産業医は、企業にとって重大な損失をもたらすリスクがあると言えるでしょう。
今回は、産業保健の領域における「医師間の書面による連携」について、ポイントを整理してご紹介します。
なお、本記事で取り上げる「診療情報提供書」と「診療情報提供依頼書」は、あくまで産業保健分野における用法に基づいて説明しています。医療機関における診療の現場では、これらの用語が異なる意味合いを持つこともありますので、その点には十分ご留意ください。
記事をご覧になる際は、どちらの書類に関する内容か、またどのような文脈で用いられているかを意識しながら読み進めていただければ幸いです。
- 診療情報提供書・・・診療の情報を産業医または主治医に伝える文書
通常は、主治医が診療内容を産業医に伝える際に用いられます。たとえば、病状の経過や診断結果、治療内容、就業に関する医学的意見などが記載されます。
一方で、私自身が産業医として面談を行った結果、「このような就業上の配慮を実施しました」という内容を主治医に報告するための文書を作成することもあります。これは、医師間での情報共有を目的としたものであり、連携を深めるために非常に有効な手段です。
なお、一般的に「紹介状」や「主治医の意見書」と呼ばれる文書も、この診療情報提供書に該当します。 - 診療情報提供依頼書・・診療の情報を相手方医師からもらうために依頼するための書面
産業保健の分野においては、通常、産業医が主治医に対して診療情報提供書を依頼するかたちで情報のやり取りが行われます。
この際に用いられる文書には、本人の個人情報の開示に関する同意文が記載されていることが一般的です。これは、本人のプライバシーを尊重しつつ、職場復帰支援や両立支援を円滑に進めるために欠かせない手続きです。
私が最も頻繁に発行する書面は、診療情報提供依頼書です。
また、先述のとおり、産業医としての面談結果を診療情報提供書の形式で主治医に送付する場合もあります。たとえば、主治医が「復職可能」と判断している一方で、産業医が「復職不可」と判断した場合など、その理由や状況を任意の書面として主治医にお伝えするケースが該当します。
なお、医療情報は個人情報保護法における「要配慮個人情報」に該当します。そのため、これらの情報を取り扱う際には、個人情報の保護に十分な配慮が求められます。
個人情報保護法2条2項 (定義)
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
e-Gov 個人情報保護法
医療情報の取り扱いには、非常に慎重な配慮が求められます。
通常、診療情報提供依頼書は本人に手渡しし、本人から主治医へ提出してもらう方法が一般的です。しかし、場合によっては産業医が直接主治医に送付する必要があることもあります。
このような状況で診療情報提供依頼書を送付しても、主治医からの返答が得られないことがあります。これは、主治医が多忙で対応に時間を要している場合や、本人との面談のうえで書面を作成したいと考えているため、本人の次回受診を待っていることが理由です。
ただし、まれに主治医のもとに書面が届いていなかったというケースも発生します。さらに、本人の申告内容や過去の経緯を踏まえ、主治医からの適切な返答が得られない可能性があると判断されることもあります。
このようなリスクを避けるためには、レターパックや特定記録郵便など、確実に到達を証明できる送付方法を活用することが重要です。
レターパックと特定記録
「特定記録郵便」という制度をご存じでしょうか?
以下に、その概要と使い方をご紹介します。
「郵便物やゆうメールの引受けを記録するサービスです。配達の際は受取人さまの郵便受箱に配達します。」
「郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」に必要事項を記入し窓口にお出しください。」
郵便局ホームぺージ
とはいえ、郵便局まで出向くのが面倒なときもありますよね。そんなときに便利なのが、郵便局が提供する「レターパック」です。レターパックには「レターパックライト」と「レターパックプラス」の2種類があります。
レターパックライトは青色の封筒で、一般的には「青レターパック」と呼ばれます。一方、レターパックプラスは赤色で、「赤レターパック」として親しまれています。
いずれも書面を封入したあと、追跡用の「保管用シール」を剥がして手元に保管し、郵便ポストに投函するだけで送付できます。保管用シールに記載された番号を使って、郵便局のウェブサイトなどで配達状況を確認することができます。
青レターパックは「郵便受けへお届けします」。
赤レターパックは「対面でお届けし、受領印又は署名をいただきます」。
とのことです。
私は、診療情報提供依頼書を作成する際、本人の同意を得たうえで、どうしても主治医が書面を受け取ったことを確認したい場合には、赤レターパック(レターパックプラス)を使用することが多いです。もちろん、行政書士事務所としては内容証明郵便を用いることも可能ですが、それでは手間がかかりますし、受け取る側にとっても仰々しい印象を与えてしまいます。
また、レターパックは返信用としても活用できるため非常に便利です。あらかじめ自分の住所を宛先として記入したレターパックを、送付する書類と一緒に同封すれば、相手がそのまま返送に使用できます。このときも、返信用レターパックの「保管用シール」は剥がして手元に保管し、追跡番号を控えておくことで、返送状況を確認することが可能です。
まとめ
産業医と主治医との間では、診療情報のやり取りが日常的に行われており、通常は「診療情報提供書」や「診療情報提供依頼書」といった書面を用いて情報交換がなされます。多くの場合、受診者本人がこれらの書類を主治医へ持参しますが、状況によっては産業医が主治医へ直接書面を送付することもあります。
診療情報提供書は、主治医が診療内容や意見を産業医に伝えるもので、就業上の配慮に関する産業医から主治医への報告も含まれます。一方、診療情報提供依頼書は、産業医が主治医に情報提供を求める際に使用され、本人の同意を得て発行されます。
これらの情報は、個人情報保護法において「要配慮個人情報」に該当し、厳格な取扱いが求められます。本人のプライバシーを守るため、情報のやり取りには慎重な対応が必要です。
書面送付後、主治医からの返答が遅れたり、届いていないと言われるケースもあります。このようなトラブルを避けるため、確実に到達が確認できる送付方法を選ぶことが重要です。
特定記録郵便やレターパック(特に対面配達と受領印があるレターパックプラス)は、追跡が可能で、到達確認に有効です。また、返信用のレターパックを同封することで、スムーズな返送が期待でき、やり取りの効率も向上します。
主治医との連携は、職場復帰支援や治療と仕事の両立支援を成功させるために不可欠な要素であり、産業医はその重要性を理解したうえで、適切な手段と配慮をもって実務にあたる必要があります。
労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。