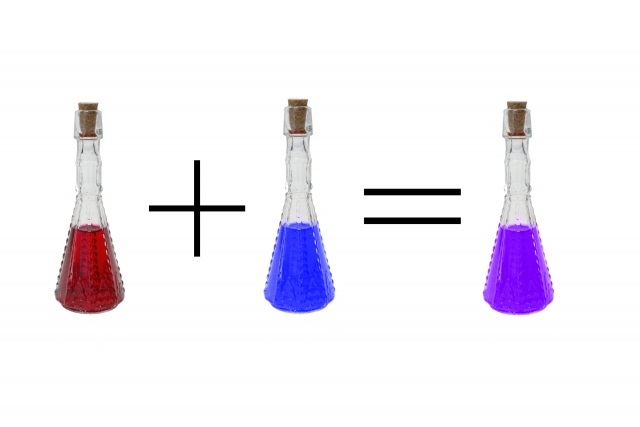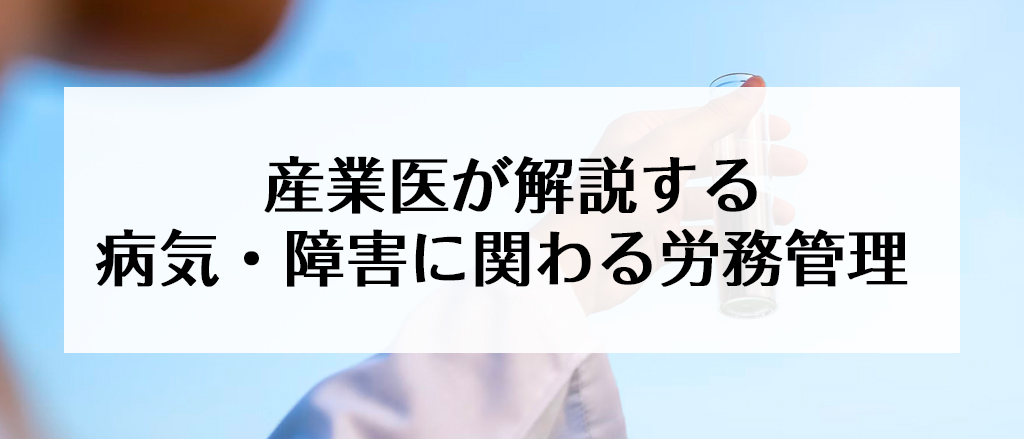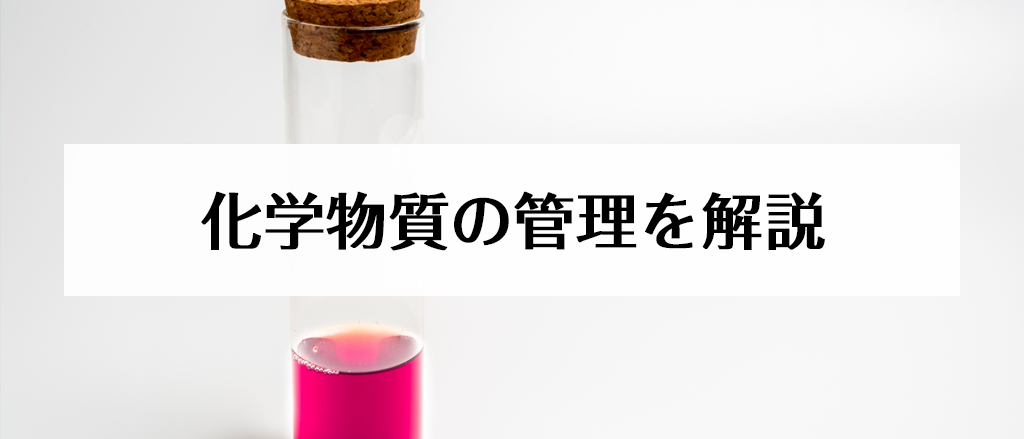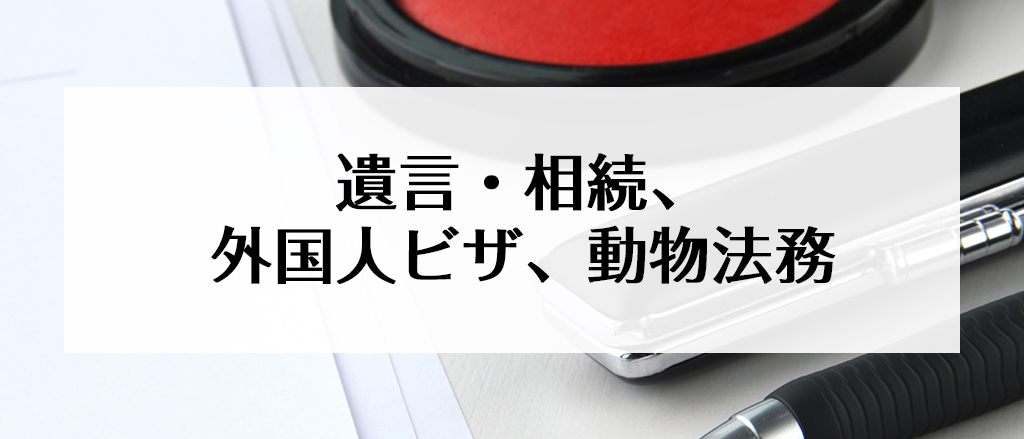2024/02/13 2023/04/13
【安全衛生・人事労務担当者向け】有機溶剤の作業環境測定の法令の規定についてわかりやすく説明

有機溶剤を取り扱う場合、作業環境測定が必要です。
このため、今回は有機溶剤の作業環境測定に関する法令について解説いたします。
今回は条文が複雑なので、条文と解説のハイライトの色を同色にしました。
有機溶剤の法令上の作業環境測定の規定について解説
労働安全衛生法65条で作業環境測定が義務付けられている
労働安全衛生法65条に作業環境測定の規定があります。こちらは、有機溶剤についてのみではなく、特化物や鉛など他の化学物質についても適用されます。
ここで、安全衛生のプロとして、ぜひ知っておいてほしいことがあります。それは・・・
「作業環境測定」は、労働安全衛生法65条に基づくものです。
これは、な「ぜ重要なのかというと、作業環境の測定については、個人サンプリング法や、個人ばく露測定などがあります。個人ばく露測定については、労働安全衛生法65条の作業環境測定に当たりません。
同様に、化学物質の自律的管理において、濃度基準値設定物質について化学物質の濃度を実際に測定する場合(実測法)、この測定は労働安全衛生法65条の作業環境測定に当たりません。
例えば、産業医が「作業環境測定の個人ばく露測定を行いましょう」というのは法令上、間違いとなります。
では、実際に、労働安全衛生法65条を見てみましょう。労働安全衛生法65条は、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の事業場で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならないと定めています。
つまり、 労働安全衛生法65条で作業環境測定が義務付けられています。
労働安全衛生法(作業環境測定)第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
e-Gov 労働安全衛生法
さらに政令で、詳しく作業環境測定を行うべき作業場が定められています
ここで労働安全衛生法65条1項には、作業環境測定を行うべき物質について定めがあり、65条中の「政令に定めるもの」(労働安全衛生法65条、緑ハイライト)とあります。
この「政令に定めるもの」ですが、政令は具体的には労働安全衛生法施行令21条1項10号となります。
この労働安全衛生法施行令21条1項10号は「令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務」として、この後も登場しますので覚えておきましょう。
この労働安全衛生法施行令21条1項10号は、作業環境測定を行うべき作業場を列挙しており、重要な条文です。
(ポイント)
「令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務」とは
別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
になります。
以下が、「令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務」です。
労働安全衛生法施行令21条には、作業環境測定を行うべき作業場が定められていますが。
その一つということです。
労働安全衛生法施行令
(作業環境測定を行うべき作業場)第二十一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
これを見ていくと、労働安全衛生法施行令21条1項10号に、「別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場 」と記載があります。
ここでまた、別の法令を参照していますね。今度は「別表6の2」です。
では、別表6の2はというと以下のように、有機溶剤をすべて列挙しています。つまり第1種、第2種、第3種有機溶剤のすべて有機溶剤となります。
「削除」が多いですよね、実は14はクロロホルム、23は四塩化炭素などは特別有機溶剤として単なる有機則の有機溶剤から、特化物へ移行したので削除されているのです。
ここで、1号から47号までが第1種と第2種の有機溶剤となり、48号以下は第三種有機溶剤になります。
ポイント
「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務」
とは、第1種有機溶剤と、第2種有機溶剤を扱う業務のことです。
労働安全衛生法施行令
別表第六の二 有機溶剤(第六条、第二十一条、第二十二条関係)一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
十 オルト―ジクロルベンゼン
十一 キシレン
十二 クレゾール
十三 クロルベンゼン
十四 削除
十五 酢酸イソブチル
十六 酢酸イソプロピル
十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
十八 酢酸エチル
十九 酢酸ノルマル―ブチル
二十 酢酸ノルマル―プロピル
二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
二十二 酢酸メチル
二十三 削除
二十四 シクロヘキサノール
二十五 シクロヘキサノン
二十六及び二十七 削除
二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
二十九 削除
三十 N・N―ジメチルホルムアミド
三十一から三十三まで 削除
三十四 テトラヒドロフラン
三十五 一・一・一―トリクロルエタン
三十六 削除
三十七 トルエン
三十八 二硫化炭素
三十九 ノルマルヘキサン
四十 一―ブタノール
四十一 二―ブタノール
四十二 メタノール
四十三 削除
四十四 メチルエチルケトン
四十五 メチルシクロヘキサノール
四十六 メチルシクロヘキサノン
四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン
四十八 ガソリン
四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
五十 石油エーテル
五十一 石油ナフサ
五十二 石油ベンジン
五十三 テレビン油
五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物
化学物質として有機溶剤が含有されていても、5%以下は有機溶剤と扱わない
もう一つ、注意が必要なのは、これらの「種類」が入っているからと言ってすぐに「有機溶剤」とは言わないのです。
なぜなら、有機則1条1項2号にて、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいうと定められているので、例えば溶液に含まれる有機溶剤全体の含有率が2%とか3%だと有機溶剤にあたらないということになります。
有機溶剤中毒予防規則
(定義等)第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 有機溶剤 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。二 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。
(以下略)
e-Gov 有機溶剤中毒予防規則そして、政令の内容をさらに詳しく有機則が述べています。
そして、政令の内容をさらに詳しく有機則が述べています。
そして、有機則の測定について記載されている有機溶剤中毒予防規則28条には「令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする」とあります。
先ほどの、「令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務」が出ましたよね。
政令の作業環境測定を行うべき作業場でしたよね。
つまり、政令の「令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務」に加えて、さらに有機溶剤中毒予防規則でその範囲や測定方法につき詳細に定められているということになります。
有機溶剤中毒予防規則(測定)第二十八条 令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。3 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。一 測定日時二 測定方法三 測定箇所四 測定条件五 測定結果六 測定を実施した者の氏名
ここで「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務」とありますが、1号から47号までの有機溶剤とはなんでしょうか?
48号以下は第三種有機溶剤でしたよね。
つまり、1号から47号までの有機溶剤とは、第1種有機溶剤と第2種有機溶剤のことで、第3種有機溶剤は含みません。
したがって、原則として、第3種有機溶剤は作業環境測定をしなくていいということになります。
なお、「第3条1項の場合における」というのは、消費する有機溶剤等の量が少量で、許容濃度を超えないときは、所轄労働基準監督署長の適用除外認定を受けることができる、適用除外認定をされた場合になります。この場合、作業環境測定が必要ないということになります。
有機溶剤の作業環境測定は、C測定・D測定を行えます
従来の作業環境測定である、A測定・B測定に変わり、C測定・D測定を行うことのできる化学物質があります。
2023年10月から有機溶剤についてはすべて個人サンプリング法の適用となりました。
産業医は、C測定・D測定を適用する勘所がわかるといいでしょう。例えば、作業環境測定の結果、管理区分1であるのに、有機溶剤健診の尿中代謝物が上昇している従業員が多数存在する場合。
A測定・B測定は床から50cm以上の測定を行うが、従業員が床すれすれの空気で呼吸するような場合などにC測定・D測定を提案できるとよいでしょう。

まとめ
有機溶剤の作業環境測定について、法令の規定を以下にまとめました。
作業環境測定が義務付けられている有機溶剤は、第1種有機溶剤および第2種有機溶剤です。
また、有機溶剤を混合物中に重量の5%を超えて含有している場合、その混合物も有機溶剤として扱われます。
したがって、第1種および第2種の有機溶剤を取り扱う作業場では、作業環境測定が義務付けられます。
ただし、使用量が少なく、作業環境中の濃度が許容濃度を超えない場合は、所轄労働基準監督署長の適用除外認定を受けることが可能です。適用除外認定を受けた場合、作業環境測定の実施は不要となります。
なお、有機溶剤による作業環境測定は、個人サンプリング法が適用される場合があります。

労働衛生コンサルタント事務所LAOは、化学物質の自律的管理について、コンサルティング業務を行っております。
産業医として化学物質の自律的管理に対応可能な医師はあまりいないと思われますが、継続的なフォローも必要なため、産業医又は顧問医としての契約として、お受けしております。
個人ばく露測定のご相談やリスクアセスメント対象物健康診断の実施についても対応可能です。
化学物質の個別的な規制についても得意としています。
Zoom等のオンラインツールを用いて日本全国対応させていただいております。
詳しいサービス内容は以下のページをご参照ください。