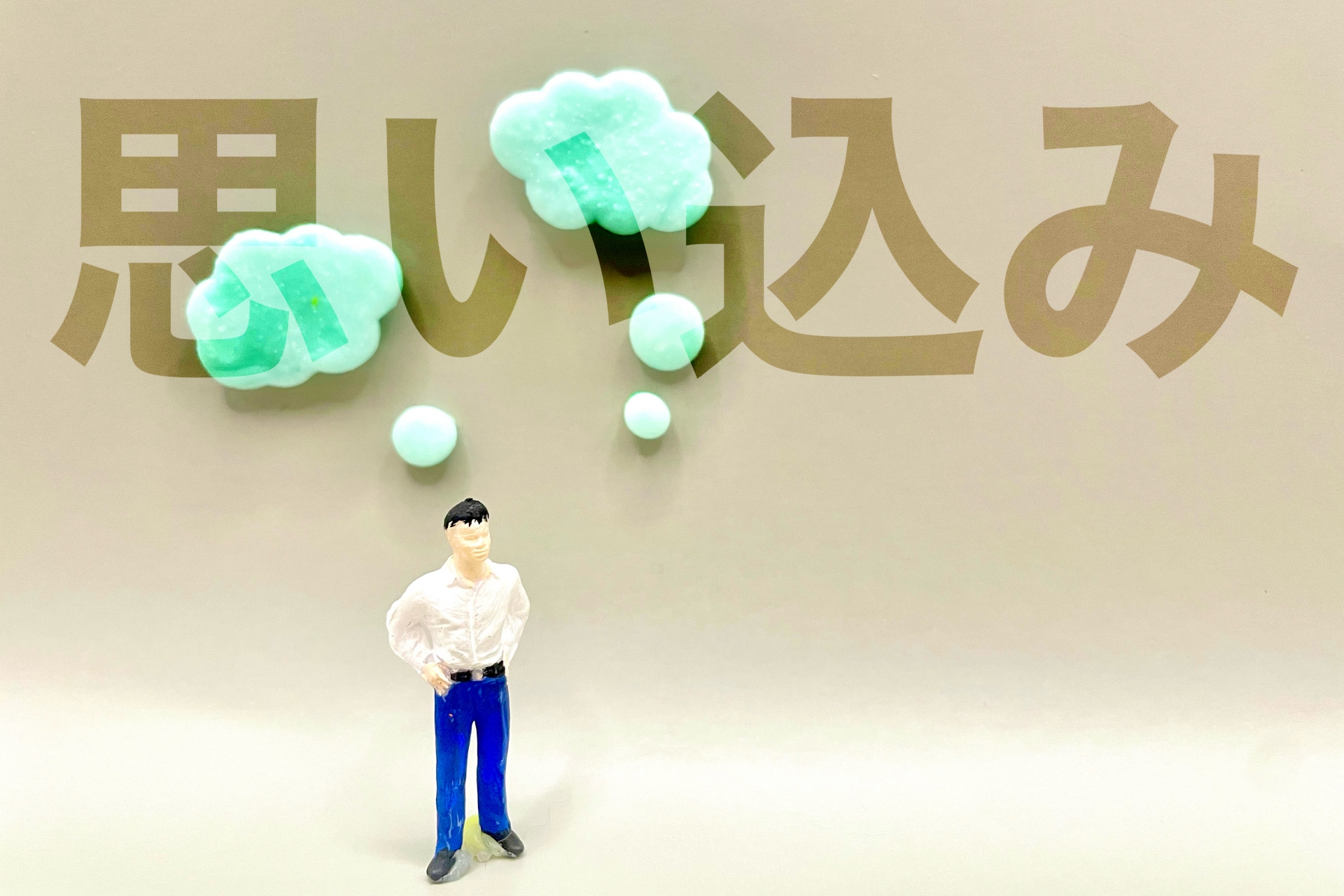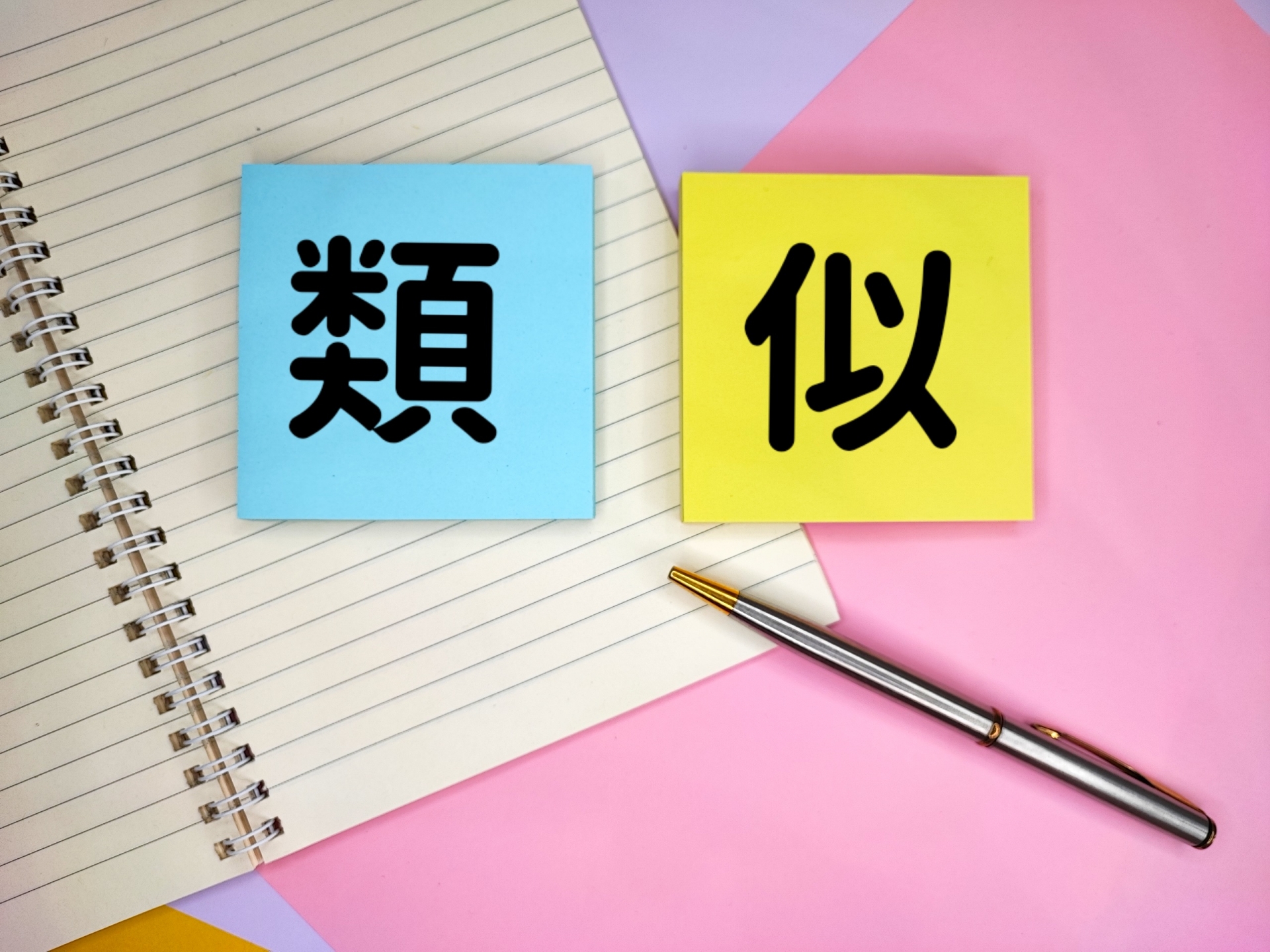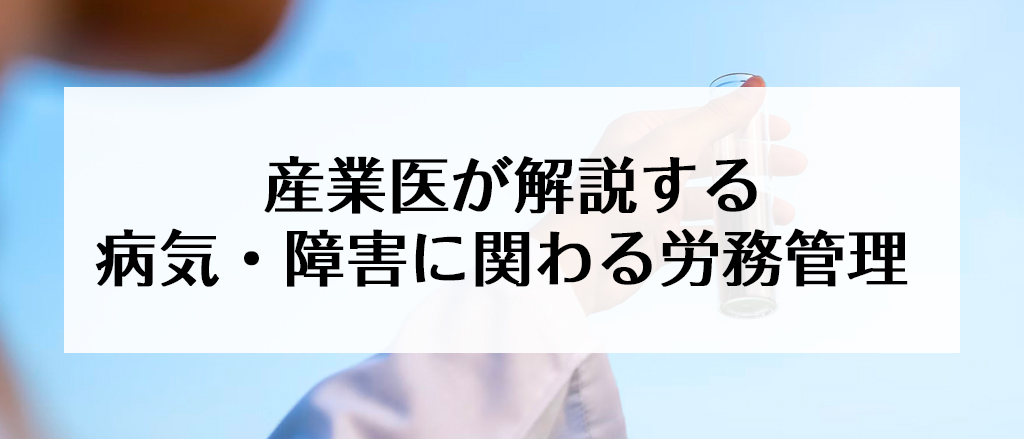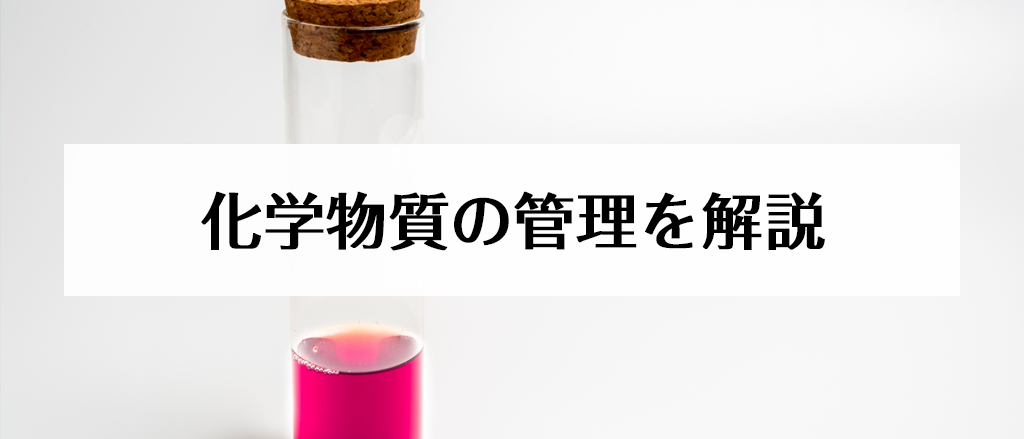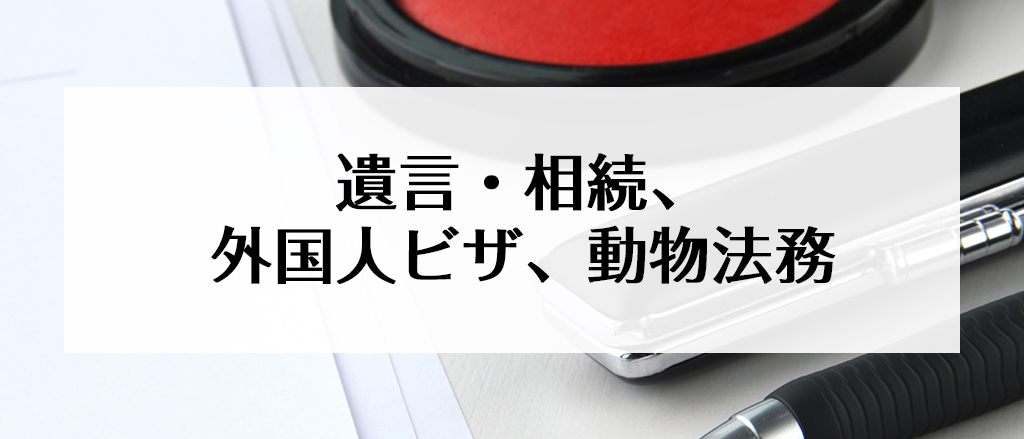キャリアコンサルタント・心理学について|士業系産業医が語る産業保健
2025/06/01 2023/04/18
【まとめ】産業保健のメンタルヘルス対策におけるシステムズアプローチについて解説
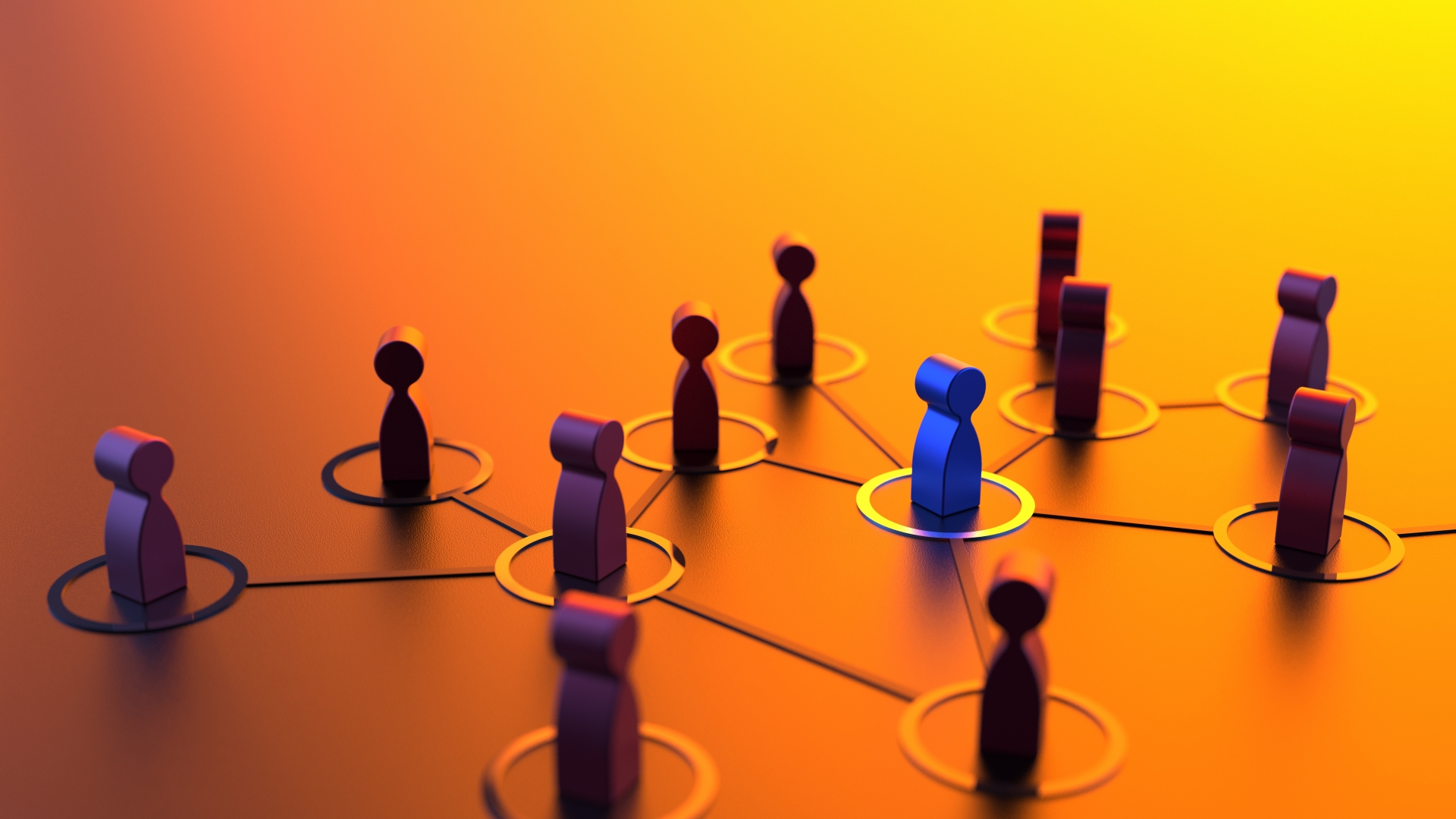
メンタルヘルス対策というと、多くの場合、メンタルヘルス不調者への対応や支援が中心になります。
確かにそれは重要な取り組みですが、私はそれだけでは根本的な解決には至らないと感じています。
そこで、公衆衛生の視点と心理学的な知見を組み合わせ、より効果的かつ構造的にメンタルヘルスを改善できないかと考えるようになりました。
その中で導き出された答えが、「システムズアプローチ」の活用です。
システムズアプローチとは、個人の問題を個人だけのものとして捉えるのではなく、職場全体の構造や関係性、組織文化などの「システム」全体を対象に介入する方法論です。
このアプローチを産業医の活動に組み込むことで、不調者が生まれにくい環境づくりや、組織としての予防的対応が可能になると考えています。
システムズアプローチの概論
はじめに
システムズアプローチを理解し活用することで、これまで組織内では見過ごされてきた構造的な要素や相互作用が「見える化」されるようになります。
その結果、これらの要素を的確に把握し、適切にマネジメントすることで、職場のさまざまな課題に対する根本的な解決の糸口が見えてくるかもしれません。
しかしながら、このアプローチは強力な分析・介入手法であるがゆえに、使い方を誤ると大きなリスクを生む可能性もあります。
特に、組織を管理・操作するための「手段」として一方的に用いられたり、力関係の維持や統制の道具として悪用されると、組織のバランスが崩れ、人間関係の破綻や精神的被害といった深刻な結果を招くこともあるのです。
やや大げさに聞こえるかもしれませんが、実際に現場では、誤った介入により、組織や個人が深く傷つく事例も存在します。
だからこそ、システムズアプローチは「理解」と「倫理」を伴った慎重な運用」が何より重要なのです。
ではここからは、システム論の実践的な視点についてお話ししたいと思います。
たとえば職場には、「管理部」「人事労務課」「営業課」などの部署があり、そこには「社長」「部長」「課長」「一般社員」といった多様な役職の人たちが存在します。
それぞれの部署・役職が相互に関係し合いながら、組織全体としてのバランスを保っている――これが、**「会社というシステム」**です。
一方、同じ個人が自宅に帰れば、「父親」「母親」「長男」「長女」など、家庭の中の役割を担い、**「家族というシステム」**にも属しています。
また、「地域のスポーツサークル」「親族の集まり」「日本という国家」といった、他の多様なシステムにも同時に関わって生きているのが、私たちの現実です。
このように、人は常に複数のシステムに属し、それぞれの中で異なる役割や関係性を持って生活しています。
システムズアプローチとは、こうした「人が属するシステム全体」に注目し、関係性や構造に働きかけることで、メンタルヘルスの不調や職場の課題を改善していく方法論です。
当事務所では、このシステムズアプローチを重視し、実践的に支援に活かしています。
システムの構造を理解し、働きかけることで、単に個人を支えるのではなく、職場全体をより健全な環境へ導くことができると考えています。
なお、本ブログでは、システムズアプローチに関する事例や理論をまとめてご紹介していますので、ご関心のある方はぜひご覧ください。
システムズアプローチの基本
「患者とみなされた者」と円環的因果律(Circular causality)
システムズアプローチを理解するうえで、ぜひ知っておきたい重要な概念に、家族療法と「患者とみなされた者(IP:Identified Patient)」があります。
システムズアプローチは、個人にではなく、その個人が属する「システム(関係性の構造)」に対して介入する手法であり、その理論的基盤のひとつに家族療法があります。
家族療法においては、表面的に問題を抱えているように見える個人が、実は家族というシステム全体の不均衡を表現している存在であると考えます。
そのため、支援を要する本人を「患者」とは呼ばず、「患者とみなされた者」=Identified Patient(IP)という位置づけで捉えます。
つまり、IPはあくまで家族システム(あるいは組織システム)の問題が表面化した象徴的な存在に過ぎない、という見方です。
この考え方をより深く理解するには、「円環的因果律(Circular Causality)」の概念が不可欠です。
これは、「誰が原因か」「何が発端か」という直線的な因果関係ではなく、構成員同士の相互作用が連続的かつ循環的に影響し合っているという視点です。
たとえば、ある社員が精神的に不安定になる背景には、本人の問題だけでなく、その職場のシステムに内在する不均衡や緊張関係が影響していることがあります。
このように、IPとは、組織や家庭に内在する問題が表面化した「氷山の一角」であり、個人だけを対象に支援するのではなく、その背景にあるシステム全体へのアプローチが求められるのです。
実際の円環的因果律の把握と例
実際に、メンタルヘルス不調者が続発している企業や組織の状況を詳細に分析してみると、円環的因果律が複雑に重層化しているケースが少なくありません。
つまり、特定の出来事や関係性が、一方向的な原因と結果ではなく、複数の要素が相互に影響し合い、問題が循環的に強化されている構造が見えてきます。
さらに注意すべきは、悪意をもった人物や操作的な関係者が、あえてこの「円環的因果が起こりやすい関係性」に介入し、意図的に問題を拡大させるような状況も実際に存在することです。
たとえば、人間関係の摩擦や誤解が繰り返し再生されるような状況を作り出し、その結果としてメンタルヘルス不調者が次々に生まれる構図が完成してしまうのです。
このような構造的問題は、「円環的因果律」という視点を知らなければ、そもそも認識することすら困難です。
表面的には個々の問題として見える出来事でも、背後にはシステム全体の歪みが潜んでいることが多く、それに気づかずに個人対応だけを続けても、問題の根本的な解決には至りません。
システムズアプローチを行う上で役に立つ理論
集団極化、同調の発生を意識しましょう
心理学の用語に「同調行動(conformity)」という概念があります。
これは、個人や集団の中で、ある行為者が他者の行動、態度、感情などに自らを合わせることを指します。多くの場合、この行動は無意識のうちに起こり、集団の調和や対立回避を目的として働くことが知られています。
そしてこの同調行動は、システムズアプローチの文脈においても非常に重要な意味を持ちます。
特に、同調行動が頻繁に起きている組織や集団においては、それによって「円環的因果律(circular causality)」が形成・強化されていると分析できる場面があります。
たとえば、職場で多数派の意見に無批判に同調する傾向が広がると、組織の構造的な課題が放置されたまま再生産され、結果的に問題の本質が見えにくくなることがあります。
このような現象は、個人の行動として見えるものが、実は集団システム全体のパターンに組み込まれていることを示しています。
したがって、同調行動の仕組みを知り、その影響を理解することは、組織内の心理的・構造的な問題にアプローチする上で極めて重要です。
システムズアプローチと認知バイアスについて
認知バイアスについて
組織内には多様な人が存在し、それぞれが独自の価値観や経験をもとに意思決定を行っています。
しかし、人間には「認知バイアス」という心理的な偏りがあるため、ときに思い込みや現実と乖離した判断を無意識のうちにしてしまうことがあります。
このような認知バイアスに対する理解は、システム(組織)に介入するうえで非常に重要な視点です。
バイアスによって意思決定や対人関係が歪められることで、円環的因果や同調行動が強化され、職場の問題が慢性化することもあるからです。
以下に、システム内で問題を引き起こしやすい代表的な認知バイアスをいくつか挙げます。
セルフサービングバイアス
セルフサービングバイアス(Self-serving bias)とは、個人が自己評価を保とうとする心理的傾向のひとつで、成功した結果は自分の能力や努力(内的要因)によるものとし、失敗や問題が起こったときは環境や他人のせい(外的要因)に帰属させる認知の歪みです。
このバイアスは、個人の心の安定を守る防衛機制として自然に働くものですが、職場や組織といったシステムの中では、問題の本質を見誤らせる要因となることがあります。
特に、セルフサービングバイアスに無自覚な人が、他者や組織構造に責任を押し付け続けることで、円環的因果律(circular causality)が強化され、組織内の不調が慢性化する要因となることもあります。
したがって、セルフサービングバイアスは、システムの健全性を損なう「避けるべき認知バイアス」の一つです。
このバイアスに気づき、自己評価を見直す習慣を持つことは、個人の成長だけでなく、組織の改善にもつながります。
対応バイアス(correspondence bias)
円環的因果関係が生じる背景には、「対応バイアス(correspondence bias)」が関与している可能性があります。
対応バイアスとは、他者の行動の原因を、その人の性格や意図など「内的要因」に過度に帰属させてしまう傾向を指します。
このバイアスが生じる大きな要因の一つが、状況に関する情報の不足です。
つまり、状況を正しく把握していないと、ある人がなぜそのような行動を取ったのかを正確に理解できず、誤った因果関係の認識が組織内に蓄積されてしまうのです。これが結果として、円環的因果を助長し、問題が慢性化・複雑化する要因となり得ます。
このような問題の防止・是正のためには、システム内のメンバー同士が正確な情報を共有し、状況を理解するための「コミュニケーションの促進」が非常に重要です。
たとえば、キャリアコンサルティング(キャリコン)の場では、上司や部下、同僚との円滑な対話の重要性がよく提案されます。
このようなコミュニケーション機会を通じて、システム内の構成員が互いの置かれた状況や背景を理解し合うことで、対応バイアスの解除や予防につながります。
したがって、誤解の連鎖や関係性の悪化を防ぐためにも、情報の開示と対話の場を組織的に設けることが、システムの健全性を保つカギとなるのです。
サリエンス バイアス
サリエンス・バイアス(salience bias)とは、目立つ情報や要素に強く注意を向ける一方で、目立たない情報を軽視・無視してしまう傾向を指します。
このバイアスは私たちの日常の意思決定にも深く関わっており、ときに判断を誤らせる要因となることがあります。
特に組織や企業の中では、注目を集めやすい問題や目立つ人物には対応が集中する一方で、あまり表面化しない問題が後回しにされがちです。
この結果、一見些細に見える目立たない問題が放置され、やがて重大な問題へと発展するケースもあります。
このようなサリエンス・バイアスを回避・補正するための有効な手法の一つが、システムズアプローチです。
システムズアプローチでは、表面に現れた現象だけでなく、背後にある関係性や構造、周辺環境といった目立たない要素にも意識的に注目します。
つまり、目立たないが重要な要素を見逃さず、全体の構造的バランスを観察・理解しながら介入していくことで、サリエンス・バイアスによる誤判断や対応の偏りを防ぐことが可能となります。
ヒューリスティックについて
まず押さえておきたい重要な概念に、ヒューリスティック(heuristic)があります。
ヒューリスティックとは、経験や直感に基づいて迅速に意思決定を行うための思考の簡略化手法であり、
「このような状況では、こうすればうまくいく」「以前にも似た経験がある」といった、過去の経験を活用して複数の選択肢から最適なものを選ぶ方法です。
このヒューリスティックには、以下のような大きなメリットがあります。
複雑な状況でも即座に判断を下せる
経験則に基づいた効率的な意思決定が可能
感情的・身体的負担を軽減できる
しかしながら、ヒューリスティックにはデメリットも存在し、特にシステムズアプローチの観点では問題となる場面が少なくありません。
たとえば、ヒューリスティックが過度に働くと、本来は新たな視点や構造的な理解が求められる状況に対しても、過去の経験だけで判断し、誤った対応を取ってしまうことがあります。
結果として、システム全体の構造や円環的因果の存在に気づけず、問題の再発や拡大を招く可能性があるのです。
システムズアプローチでは、個人の経験則に依存するだけでなく、システム全体の相互作用や関係性を観察・分析することが不可欠です。
そのため、ヒューリスティックを有効に活かしつつも、それに依存しすぎない柔軟な思考が求められます。
代表性ヒューリスティック(Representativeness heuristic)
代表性ヒューリスティック(Representativeness heuristic)とは、ある出来事の可能性や確率を評価する際に、それが過去の代表的・典型的な事例とどれだけ似ているかによって判断してしまう思考の傾向です。たとえば、「以前に似たようなケースがあったから、今回も同じような結果になるはずだ」といった推論がこれに当たります。
このヒューリスティックは、日常の迅速な意思決定に役立つ一方で、現在の状況や文脈に過去の事例が必ずしも適合しない場合、誤った判断や対応を招くリスクがあります。
特に、時代や環境が急速に変化している現代においては、過去の「代表的な事例」がもはや適用できないケースも少なくありません。
それにもかかわらず、古い事例を基準に現状を評価してしまうと、誤解や思い込みが重なり、結果的に円環的因果関係(circular causality)を引き起こす要因となることがあります。
つまり、ある判断の誤りが組織や人間関係の中で相互に影響を及ぼし合い、問題の再生産や慢性化を促す構造が生じるのです。
このような誤ったパターンを避けるためには、過去の事例に頼りすぎず、常に現状の文脈や構造を新たな視点でとらえる柔軟性が重要です。
システムズアプローチは、こうした固定化された思考に対抗するための有効な視座を提供します。
利用可能性ヒューリスティック
利用可能性ヒューリスティック(Availability heuristic)とは、思い出しやすい情報や印象に基づいて意思決定を行う心理的傾向のことを指します。
また、十分な情報が得られていない状況下で、限られた記憶や経験に頼って判断を下すことも含まれます。
このヒューリスティックは、日常的な意思決定をスムーズに進める助けにはなるものの、ときに誤った認識や判断を引き起こすリスクがあります。
たとえば、過去に印象に残った強烈な出来事や、最近目にしたニュースなどが頭に浮かぶと、それが実際以上に頻繁で重要だと錯覚してしまうのです。
このような思考の偏りは、職場における意思決定や人間関係の判断にも影響を及ぼすため、特にシステムズアプローチの観点からは注意が必要です。
なお、このテーマには多くの実務的・理論的な論点がありますので、詳しくは以下の記事をご参照ください。
システムズアプローチと、キャリアコンサルタント、心理カウンセラーの関係
実は、システムズアプローチ(特に家族システム論)は、キャリアコンサルタントと心理カウンセラーのいずれにとっても非常に有用かつ重要な学習分野です。
なぜなら、このアプローチは個人を「孤立した存在」として見るのではなく、その人が属する家族、職場、組織などのシステムとの関係性に注目し、相互作用の中で問題を理解・支援する枠組みを提供してくれるからです。
とはいえ、キャリアコンサルタントにとっては、システムズアプローチの中でも特に「同調行動」「認知バイアス」「ヒューリスティック」など心理学に基づく概念について、学ぶ機会が限られていることも多いのが実情です。
これらの要素は、表面化しにくい職場の構造的課題や個人の意思決定の歪みを理解する上で極めて重要であるにもかかわらず、実務教育や研修の中では必ずしも十分に扱われていないことがあります。
一方で、心理カウンセラーにとっては、心の問題を扱う訓練は豊富であっても、キャリア形成や職場における人間関係、組織構造といった領域におけるシステムズアプローチの応用には、やや戸惑いや限界を感じるケースもあります。
特に、「仕事」という文脈における人間の行動や葛藤には、心理的な要因に加え、制度・役割・権力構造といった社会的・組織的背景が深く関与しているため、心理学だけでは読み解けない場面が多々存在するのです。
したがって、理想的には、心理系カウンセリングとキャリア系カウンセリングの両方の視点を統合的に学ぶことが望ましく、またそれによって異なる専門領域の協働や連携が生まれることが重要です。そうすることで、クライエントを取り巻くシステムを俯瞰し、より多角的・構造的にアプローチできる支援者としての実践が可能になります。
まとめ
メンタルヘルス対策は、これまで「不調者への個別支援」が中心でしたが、それだけでは根本的な改善にはつながりません。
本記事でご紹介したように、個人を取り巻く**職場や家庭などの「システム」全体に着目し、関係性や構造そのものに働きかける「システムズアプローチ」**は、より持続可能で実効性の高いメンタルヘルス対策を実現するための有力な視点となります。
このアプローチを実践するには、「円環的因果律」や「同調行動」、「認知バイアス」や「ヒューリスティック」など、心理学的な知見と組織論的な理解を統合して活用する視野の広さと深さが求められます。
また、産業医、キャリアコンサルタント、心理カウンセラーなど専門職がそれぞれの立場に閉じず、分野を横断的に学び合い、協働して支援に取り組む姿勢が、真の意味での組織改善とクライエント支援につながるでしょう。
私たちは誰もが複数の「システム」に属して生活しています。
だからこそ、目の前の個人の問題を「その人だけの課題」として見るのではなく、その背景にあるシステムの影響を読み解く力が、今後ますます重要になっていくはずです。
システムズアプローチを通じて、組織全体をより健全な方向へと導く視点と実践力を、ぜひ取り入れてみてください。
労働衛生コンサルタント事務所LAOでは、産業医・顧問医の受託をお受けしております。労務管理と一体になった産業保健業務を多職種連携で行います。